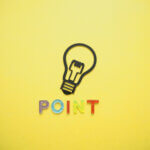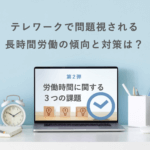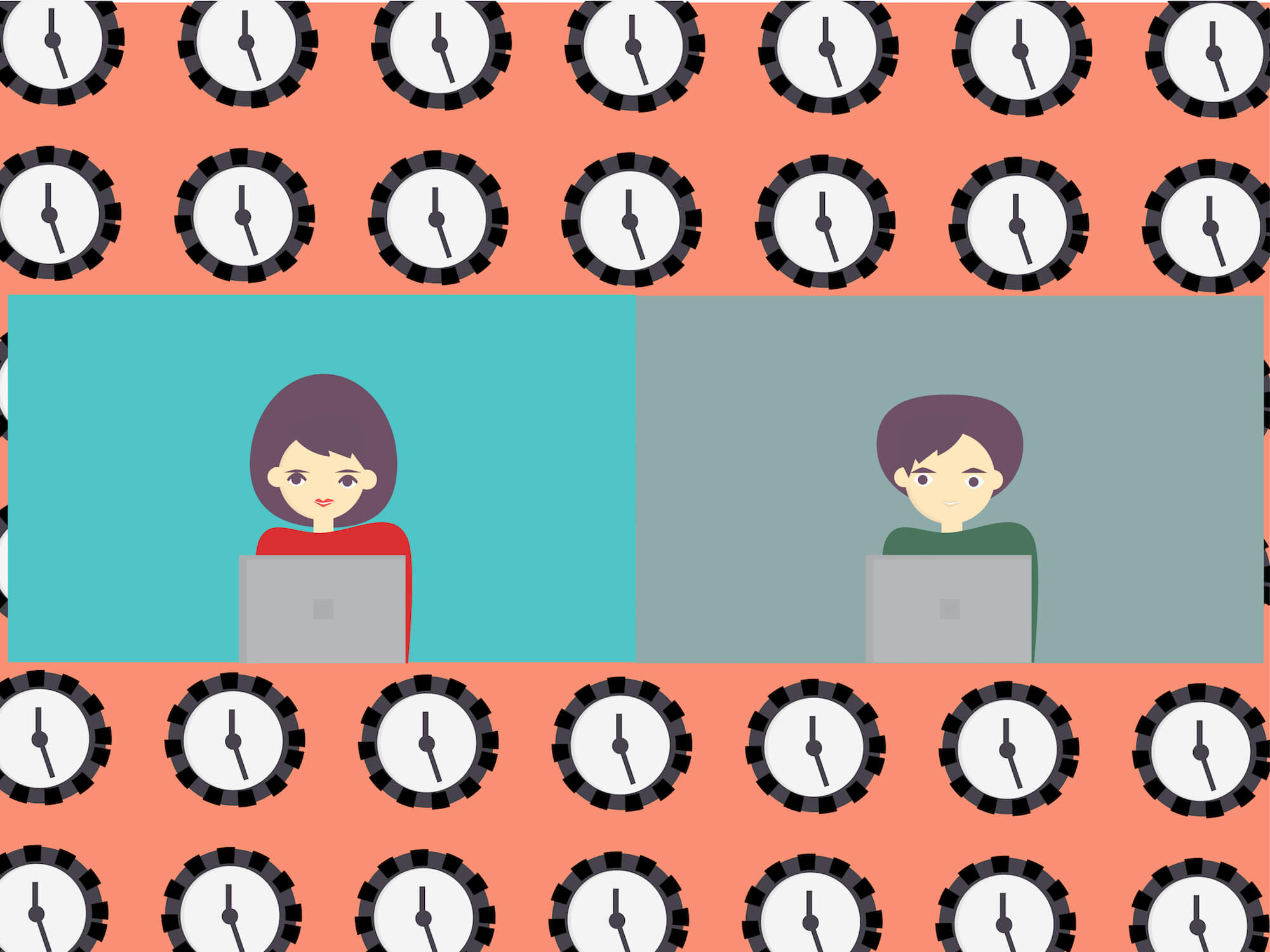
労働安全衛生法は、労働者の安全や健康に関するルールを定めた法律です。安全や健康に関するルールが幅広く定められているのですが、近年は長時間労働による健康被害が大きな問題となっています。
そこで本稿では、労働安全衛生法に定められている労働時間に関するルールをピックアップして、詳しく見ていきたいと思います。
労働基準法と労働安全衛生法の関係
労働基準法では、法定労働時間は1日8時間以内、1週40時間以内であるとか、時間外労働を行わせるためには36協定を結ばなければならないとか、形式的な面で労働時間の規制をしています。
これに対し、労働安全衛生法では、労働者の健康管理という観点から、より実質的な面で労働時間に関するルールが定められています。本稿ではとくに重要と考えられるルールを3つ紹介します。
健康診断に結果に基づく労働時間の短縮等
第1は、健康診断の事後的フォローに関するルールです。
事業主は年1回の定期健康診断など、労働安全衛生法で定められた健康診断を行わなければならないことは周知のとおりですが、単に健康診断を行うだけでは法律上の義務を果たしたとは言えません。
事業主は、健康診断の結果に基づき労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴取し、必要があるときは、労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないとされているのです。
ですから、具体的に「何時間以下にしなければならない」とまでは定められていないのですが、過重労働気味の労働者がいた場合は、産業医など医師の意見をよく聞いて、適切な時間数まで労働時間を減らさなければならないということです。
労働時間短縮などの措置を怠った結果、当該労働者が過労死したり、うつ病になったり、うつ病で自殺するようなことがあれば、労災ということになりますし、労災でカバーされない部分の遺失利益や慰謝料などは事業主が損害賠償を行わなければなりません。
長時間労働者への医師による面接指導の実施
第2は、長時間労働者に対するケアの観点からのルールです。
平成17年の労働安全衛生法の改正で、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられました。
具体的には、「週40時間を越える労働が1月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が見られる労働者が申し出たときは、事業者は、医師による面接指導を行わなければない」ということと、「それ以外の労働者についても、長時間の労働により疲労の蓄積が見られる者や、健康上の不安を有している労働者などについて、事業者は医師による面接指導またはこれに準ずる措置を取らなければなない」という2つのルールがこのとき労働安全衛生法に加えられたのです。
1か月の労働が100時間を超えるというのは、労災の認定などでも使われる、いわゆる「過労死ライン」の基準とされている時間数で、1か月でも100時間を超える時間外労働があれば、過労死のリスクが高いとされいます。ですから、このようなリスクに直面している労働者から申し出があった場合は、事業主は必ず医師による面接指導を行わなければならないということになったのです。
なお、今後、面接指導実施の義務は100時間から80時間に引き下げられる予定です。
使用者の労働時間把握義務
第3は、働き方改革法案成立に伴う、労働時間管理全般に関するルールです。
平成30年6月29日に働き方改革法案が成立しましたが、働き方改革法案の中には労働安全衛生法の改正も含まれています。働き方改革法案に伴う労働安全衛生法の改正では、事業主に労働時間の把握が義務化されました。施行は平成31年4月1日からです。
これまで、事業主の労働時間把握義務は、実は法律上明文化されていませんでした。労働基準法で法定三帳簿の1つとして出勤簿の作成が義務付けられていることや、厚生労働省の通達などを根拠に事業主は労働者の労働時間を把握しなければならないと一応は考えられていたのですが、今回の法改正でようやく法律上明確になったということです。
労働時間の把握義務が、なぜ労働基準法ではなく労働安全衛生法に織り込まれたなのですが、それは、先ほど説明した平成17年度改正で追加された長時間労働者に対する医師による面接指導の実効性の担保と密接に関連しているからです。
労働時間数を確実に把握できる仕組みがなければ、100時間を超えたかどうかも確認することができず、医師による面接指導は形骸化してしまうので、労働時間の把握は健康管理の観点から重要であるとして、労働安全衛生法に盛り込まれたのです。ですから、労働時間の把握対象には、労働基準法では残業代の支払いの対象とはならない管理監督者も含まれます。
労働安全衛生のために、適切な勤怠管理な必須中の必須
これまで、労働時間の把握というと、残業代の支払い漏れがないようにするなど、どちらかといえば金銭面の理由が主たるものでした。しかしながら、今後は、残業代の払い漏れがないことは当然として、企業は、健康管理のために、管理監督者も含めた従業員の労働時間の把握義務を果たしていかなければならないという時代になったということです。
そのことを認識のうえ、クラウド勤怠システムなども活用しながら、労働者の労働時間をしっかりと把握できる社内体制を構築していってください。
無料のクラウド勤怠システムIEYASUをぜひご活用ください。