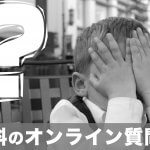まだ、勤怠管理システムを導入していない会社では、タイムレコーダー(タームカード)による打刻と、実績管理表等を利用して二重で勤怠管理をしている会社もあるかと思います。
その際に問題になるのが、タイムレコーダー(タームカード)の打刻と実績管理表等の齟齬や乖離です。
もし、齟齬や乖離が生じている場合どのような問題が危惧されるのかということについて、今号ではまとめていきます。
労働基準監督署からの指摘やトラブルにつながる
齟齬が生じていることで、例えば未払い賃金が生じて労働基準監督署から指摘されたり、社員とのトラブルにつながることが危惧されます。
労働時間の実態とデータの間に齟齬が生じてしまう原因は、大きく3つほど考えられます。
・従業員によるタイムカード不正打刻
不正な打刻であってもタイムカードの記録は労働時間の客観的な証拠となります(判例あり)。
・手書きの日報など(自己申告制の労働時間管理方法)による不正な自己申告
誤った数値の記入、悪意を持っての虚偽報告、企業側による労働者への圧力による虚偽申告などがあります。
・定期的な実態調査を行っていない
厚生労働省のガイドラインでは、労働者への定期的なヒアリングのほか、入退室の記録、パソコンのログイン履歴など客観的な記録を比較材料として使う方法が推奨されています。
実態と記録の間を改善していくことの定めがあれば違法ではありませんが、労働時間の把握義務は免れませんので、定期的に実態調査を行い、乖離をなくす方法を考えることが望ましいです。
実態の把握が勤怠管理の第1歩です。
退職後に従業員が「残業代未払」や「不当な残業の強制」を労働基準監督署に訴えるケースがあります。退勤打刻は記録されているが、PCログを取ってみたら乖離が発覚し遡及対応というケースを何かしらの形で聞いたことがあるかと思います。
そんな時、現場の責任者が「本人も了承していました」と口にするケースは少なからず起こる事です。その時は実労働と勤怠が乖離するいわゆるサービス残業を部下が容認した。それが恒常的に行われていて、いざ退職となった際に労働基準監督署に不服を申し立て上述したケースとなる訳です。
実際「働き方改革」から残業時間を厳しく管理することが実際の勤務状況を隠す行為を生んでいることは否定できないでしょう。
残業時間の管理、残業時間の抑制はどの企業でも課題ですが、抑圧した勤怠管理は勤怠不正を起こすきっかけにもなります。実情をしっかり把握することが大切です。
勤怠システム等を駆使し実情把握を
実情を知らずして正確な勤怠管理は不可能です。
正しい実情の把握には、「勤怠をありのままに記録すること」が第1歩となります。意識の徹底をしましょう。
実情を把握し分析することで勤怠管理の課題が浮き彫りになってくるはずです。
勤怠システムを駆使することによりあらゆる角度から勤怠管理を分析する事ができます。
紙で勤怠管理をしている企業は勤怠システム導入を検討する、既に導入している企業は一人一人が正しく勤怠システムを使用するように働きかけ使用の実態を把握し改善していく等、地道な事ではありますが、意識を変えていくことが大切です。
無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUは初期費用・月額費用が0円の完全無料でご利用いただくことができ、在宅勤務、フレックス勤務等様々な勤務体系にも対応可能です。ぜひ勤怠管理体制を整備する際に導入のご検討ください。
困ったら専門家に相談することを検討
労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください