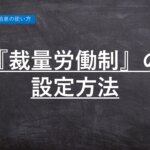「振替休日」と「代休」この違いを即答できなかった経営者と管理部長は1秒でも早く本記事を読んで学びましょう。「知らなかった」では済まされない経営リスクが潜んでいます。
給与額にも差がでる!?「振替休日」か「代休」かの違い
皆さんは、「振替休日」と「代休」の違いをご存知でしょうか?
これらは共に、「休みの日に働いた分、別の日に休むことができる」という趣旨では非常に似通っていますが、労務管理の観点で言えばまったく別ものの制度です。詳しくは後述しますが、どちらで処理するかによってお給料の額が変わります。
正しく運用できていないがために、「知らないうちに未払い賃金が発生」というケースは決して珍しくありません。何かのきっかけで未払いが判明し、全従業員に対して遡って支給するとなれば、その額は相当のものになるでしょう。「知らなかった」で済まされる問題ではありません。
企業の事業主、労務担当者であれば、今一度「振替休日」と「代休」を正しく理解し、適切な運用を心がけましょう。
事前の手続きが必須な「振替休日」と、事後処理の「代休」
まずはそれぞれの定義について、確認しておきましょう。
- 振替休日
あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること
- 代休
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの
参照:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
振替休日の場合、休日労働やその後の休日取得が生じる以前に“労働日と休日の交換”が行われるため、もともとの休日に働く分は休日労働の扱いではなくなります。よって、原則として割増賃金は発生しません(例外あり)。
一方、代休の場合、“休日労働をした後に休みを与える”という処理のため、既に発生してしまった休日労働を帳消しにすることは出来ません。よって、休日労働分の割増賃金の支払いが必要になります。
振替休日も代休も、制度として行う上では社内ルールとして決めておくべきことがあります。労務トラブルを回避するためにも、このあたりの体制はしっかり作り込んでおくことをお勧めします。
代休を運用する際の注意点
従業員に対して代休を付与することがある場合、必ずしも就業規則への規定をしなければならないわけではありません。ですが、制度として運用する上では、下記の内容を盛り込んでおくと安心です。
- 業務の都合により会社が必要と認める場合、代休付与することがあること
⇒代休付与の根拠規定となります
- 代休を取得できる期間(例:休日労働の翌日から1ヵ月以内 等)
⇒期間を定めておかなければ、代休制度自体がうやむやになる原因となります
- 休日労働について適用する割増賃金率(通常、法定休日労働に対しては「0.35」、法定時間外労働に対しては「0.25」です)
⇒法定休日とは、法律上定められている「週1日」(又は「4週の間に4日」)与えられる休日のこと。例えば週休2日の会社の場合、「法定休日に労働したら0.35」「法定休日ではない休日に労働したら休日割増なし、ただし1週間に40時間を超える労働については0.25」として処理します
「割増賃金率が異なると、処理が難しくなる」と感じるのであれば、法定休日か否かで割増賃金率を区別するのではなく、一律で「0.35」とする処理でも何ら問題はありません
※法定休日については、また別の機会に解説することにしましょう
- 代休日を有給にするか無給にするかの取決め(通常は、労働した日について賃金を支払い、代休日は無給とします)
⇒労働局の資料でも、この点は「就業規則等の規定による」としていることから、明記しておくべきです
加えて、代休付与の場合には必ず休日労働や時間外労働が発生するため、36協定の締結が必要になります。
振替休日を運用する際の注意点
振替休日の場合、代休とは異なり、就業規則上の規定が必須となります。具体的に盛り込むべきは下記の項目です。
- 業務の都合により会社が必要と認める場合、休日を他の労働日に振り替えることがあること
⇒休日を振り替えるための根拠規定となります
- 対象となる休日の前日までに、会社は振り替える休日を指定し、対象者に通知すること
⇒振替休日については、事前に詳細が通知されていなければなりません
具体的に網羅すべきは下記の項目です
・従業員からの届出日(もしくは会社からの命令日)
・労働日とする休日の指定
・休日に振り替える日の指定
※振替日は「4 週の範囲内」で具体的な日が明記されている必要があります
ところで、冒頭では「振替休日については原則として割増賃金は発生しません」と書きましたが、労働日と休日が週をまたぐ場合には、週の法定労働時間(原則40時間)を超える労働時間が発生するために割増賃金が発生することがあるので要注意です。
もちろん、このようなケースを想定して36協定を締結しておくのが望ましいと言えます。
まとめ
本号では「代休」と「振替休日」の違いとそれぞれの注意点について、ざっくりと概要を解説しました。実際に労働者がこれらを取得する際には、各人について適切な勤怠管理が必要になることは言うまでもありません。社員数が少ないうちはエクセル等での管理も通用するでしょうが、今後会社規模が拡大していくことを考慮すれば、早期に勤怠管理システムを導入しておくのが得策です!
勤怠状況を把握のために無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUをご利用下さい。