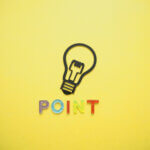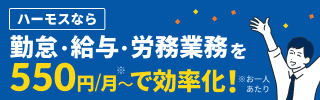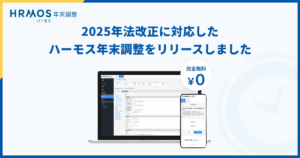従業員にお子さんが生まれた際の健康保険関連手続きは、実務ご担当者様にとって特に頭を悩ませるテーマのひとつではないでしょうか。それを裏付けるかのように、別記事『子どもが生まれた時に必要な「健康保険証交付申請手続き」を解説』は、打刻ファーストの人気記事ランキングでも常に上位となっています。
ところで、2024年12月2日の健康保険証新規発行終了に伴い、健康保険証に係る取扱いが諸々変更となっています。今号では、「新生児の健康保険証」をテーマに、お子さんが生まれた後の手続きの流れを解説しましょう。
目次
会社側の「健康保険被扶養者(異動)届」は従来通り
まず、会社側の手続きに関してはこれまで同様、生まれたお子さんを被扶養者とする手続きを行います。協会けんぽの場合、お子さんの出生日から5日以内に、協会けんぽ宛に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。以下より、様式や記入例の確認ができます。
参考:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
お子さんの「資格確認書」の要否を確認
2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行はされず、原則としてマイナンバーカードと保険証を一体化させる流れとなっています。新生児についても同様で、後述する通り、お子さんの出生後すぐにマイナンバーカードを作成し、保護者がマイナ保険証の利用手続きを行うことができます。ただし、保護者に、新生児のマイナ保険証の利用登録をする意向がない場合は、資格確認書の交付を受けることも可能です。「健康保険被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」のチェック欄があるので、保護者である従業員に確認の上、対応しましょう。
手続きには、お子さんの「マイナンバー」が必要です
「健康保険被扶養者(異動)届」では、被扶養者のマイナンバーの記入が必要で、これに関しては新生児であっても例外ではありません。赤ちゃんのマイナンバーは、マイナンバーカードの交付、または出生届後の住民票取得によって早期に確認できます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の手続きの流れは、以下の記事でも解説していますので、参考になさってみてください。
関連記事:『子どもが生まれた時に必要な「健康保険証交付申請手続き」を解説』
新生児のマイナ保険証を作るには、出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請を
ここからは、従業員側の手続きとなりますが、会社の実務ご担当者様も念のために流れを確認しておきましょう。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化促進を背景に、新生児のマイナンバーカード交付申請は、現在、出生届と併せて行えるようになっています。申請日に1歳未満のお子さんに対しては、顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用可)が交付されます。申請が受理されると、原則1週間でマイナンバーカードが届きます。里帰り先等、住民登録の住所以外に送付してもらうことも可能です。
お子さんのマイナンバーカードが届いたら、保護者が健康保険証の利用登録をします。スマートフォン端末等でマイナポータルアプリを起動し、子どものマイナンバーカードを読み取って登録を行う方法の他、医療機関・薬局のカードリーダーや、セブン銀行ATMからも健康保険証の利用登録が可能です。
顔写真なしマイナ保険証での受診時には、「暗証番号」の入力が必要
お子さんの顔写真なしマイナ保険証を利用する際の注意点として、受診時にあらかじめ保護者が設定した「4ケタの暗証番号」が必要になることが挙げられます。マイナンバーカードに顔写真がないため、オンライン資格確認システムの「顔認証モード」が使えないだけでなく、写真と本人の顔を照合することができないので、「目視モード」の使用も不可とされているためです。
マイナ保険証とは別に、各種医療証の持参が必要(2025年5月2日現在)
お子さんの受診時には、保険証の他、乳幼児医療費助成制度等の公費負担医療の医療証を利用するケースも多いと思います。このような場合、現時点では、マイナ保険証とは別に、医療証を持参する必要があります。横浜市等、マイナ保険証が医療証(小児医療証・福祉医療証・重度障害者医療証)として利用できるようになった自治体もありますが、医療機関によっては未対応のケースもあるため、医療証の持参が推奨されています。
関連記事『健康保険証新規発行停止!ご担当者様がおさえておくべき、2024年12月2日以降の健康保険実務対応』






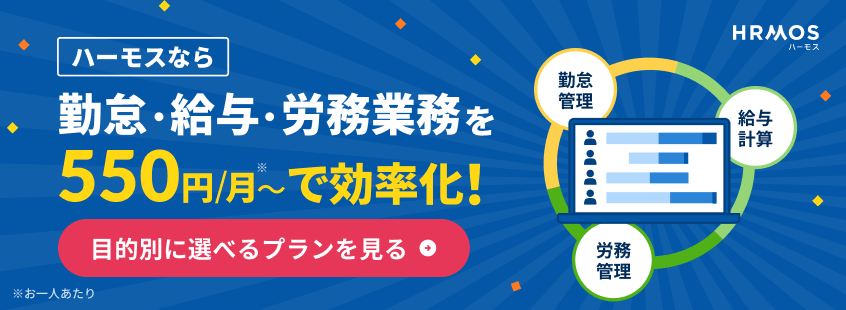
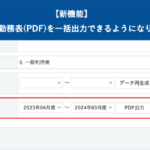


.pptx-7-150x150.png)