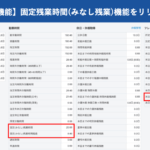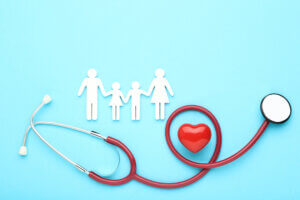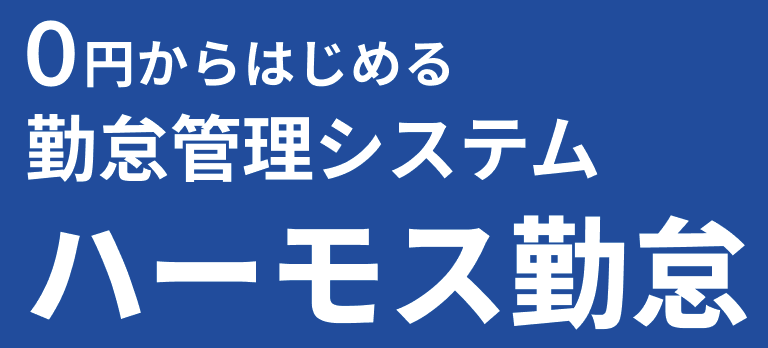「労働者性」とは一般的に雇用関係を前提として生じるものと考えられがちですが、働き方の多様化により、最近では会社と直接の雇用関係にないケースでの労働者性が問われることが増えています。とある劇団員の労働者性が争われた訴訟では、客観的に指揮命令関係があり労働者性が認められるとして、劇団側に未払賃金の支払いが命じられました。
雇用とは異なる形式で契約を締結している場合でも、労働者性があると判断されれば、働く人は労基法の適用を受けることになり、会社はその人を労働者として適切に保護しなければなりません。
雇用契約とは?業務委託との違いは?
企業が労働力を確保する方法には、自社で直接労働者を雇い入れる他、業務委託契約や派遣等雇用以外の選択肢も考えられます。働き方改革の進展は、企業側と働き手側双方に多様な就労形態に目を向けるきっかけを与えましたが、中には働き方と契約の種類が合っていないケースもあるようです。
例えば、業務委託契約について。業務委託は、業務遂行を目的とする「委任契約」と業務の成果物を目的とする「請負契約」に分かれますが、いずれも受託者の業務の進め方や働き方に対して、委託者が口出しすることはできません。受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の裁量に委ねられています。もしも委託者が直接指示を出したり、管理したりすると、受託者の労働者性が認められる可能性があり、そうなると雇用関係にある従業員同様、労基法上のあらゆる保護の対象となります。
最近では、契約上は業務委託であっても、実態としては雇用契約と疑われるようなケースが後を絶ちません。様々な契約で人を受け入れているにもかかわらず、現場では個々の契約形態への配慮を怠りがちになることもあると思いますが、後々のトラブルの引き金となる可能性がありますので注意が必要です。
労働者性の判断は、契約形態以上に実態を重視
労働者性の有無を判断する上では、「どのような契約か」よりも「実態としてどんな働き方をしているか」が重要です。労基法および労働関係法令では、具体的な労働者性の判断基準として下記の項目を挙げています。
- 仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無
- 業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
- 勤務場所・時間についての指定・管理の有無
- 労務提供の代替可能性の有無(本人に代わって補助者等が労務を提供することが認められているかどうか)
- 報酬の労働対償性(報酬が仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められている等)
- 事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額)
- 専属性の程度(特定の会社の仕事しかしてはならない)
- 公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)
これらの他、「委託先の就業規則や服務規律の適用がある」という点も、労働者性ありとの判断を裏付ける要素のひとつとなります。
雇用関係になくても「労働者性あり」とされたらどうなる?
契約上は業務委託等であっても、労働者性があると判断されるなら、働く人は労基法上の労働者として様々な保護を受けることができます。
例えば、会社は、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入や年次有給休暇の付与に対応する必要があります。また、残業代等の未払賃金があれば適正に支払わなければなりません。契約解除をする際にも、労働者性に鑑み、労基法上の解雇予告手当の支払いが求められる可能性があります。
業務量の多寡に応じて外部の労働力を活用する業務委託は、本来であれば人件費を抑えるために有効な選択肢です。しかしながら、委託側が業務委託のルールを正しく理解していなければ、働き方と契約形態のミスマッチが引き起こされることになりかねません。とりわけ、社内常駐で業務委託契約の人材を受け入れている現場では、折を見て、就労実態を確認されてみることをお勧めします。