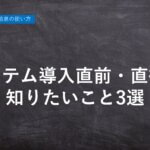改正育児・介護休業法の実務対応に、頭を悩ませてはいないでしょうか?法改正の内容は理解できても、現場において具体的に求められる「柔軟な働き方」や「個別の意向聴取」への対応に迷われるケースは多々見受けられます。今号では、厚生労働省が公開したQ&Aを元に、改正育児・介護休業法に関わる「こんな時はどうする?」の一例をご紹介しましょう。
目次
2025年改正における「個別の意向聴取」は「妊娠・出産等の申出時」と「子が3歳になる前」に実施
育児関連の「個別の周知・意向確認」については、2021年施行の改正法にすでに盛り込まれていることから、2025年改正との違いについて正しく理解しておくことが重要です。
2021年改正では、育児休業制度等に関わる周知・意向確認が求められます
2021年改正では、労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、事業主は、当該労働者に対して、育児休業制度等について周知するとともに、育児休業の取得意向を確認するための措置を講じることが義務付けられました。
2025年改正では、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する個別の意向周知・配慮が必要
一方で、2025年10月改正として義務付けられた、仕事と育児の両立に関する「個別の意向聴取・配慮」とは、以下の時期、内容について行うべきものです。
〇 実施時期
① 本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった時
② 労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
〇 意向聴取の内容
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
このように、「個別の意向聴取」の内容については、2021年改正と2025年改正とでその目的や時期、内容が異なるものです。なお、2025年改正における「配慮」の具体的な取組例としては、勤務時間帯・勤務地にかかる調整、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直しなどが考えられます。ただし、事業主として意向の内容を踏まえた検討を行った結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定していただくこととなります。
様々な働き方ごとの、「柔軟な働き方を実現するための措置」の考え方
仕事と育児の両立に関する「個別の意向聴取・配慮」同様、2025年10月施行の改正項目のひとつに、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」があります。こちらは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上構ずることを事業主に義務付けるものです。
短時間労働者やシフト制適用労働者に対する措置の具体例
柔軟な働き方を実現するための措置を検討する際、パート・アルバイト等の短時間労働者やシフト制を適用している労働者への対応に悩まれるかもしれません。以下、厚生労働省のQ&Aを参考にされると、検討にあたってのヒントを得られるかもしれません。
Q:短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。
A:パートタイム労働者等の短時間労働者であって1日の所定労働時間が6時間以下の者についても、柔軟な働き方を実現するための措置の対象となります。
事業主が短時間労働者も含めて、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮できるもの)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置で①②合わせて2つ以上講じた場合、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)の措置義務を履行したこととなります。
※ 労働者の1日の所定労働時間が6時間以下であることをもって直ちに「短時間勤務制度」の措置を講じたことにはならず、事業主は短時間勤務制度を含む5つの選択肢から、2つ以上を選択して措置する義務があります。
なお、正規・非正規で異なる措置を講じる場合、職務の内容や配置変更の範囲、その他の事情のうち、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差に当たらないようにすること、及びその理由を合理的に説明できることが求められます。
Q:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考えられますか。
A:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者も柔軟な働き方を実現するための措置の対象となります。
一般論として、例えば交替制勤務(例:早番9時~17 時、遅番 13 時~21 時)の労働者について、通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、希望したものは早番勤務のみとすることを認める措置は、柔軟な働き方を実現するための措置のうち「始業時刻等の変更」を措置したこととなります。
一方で、シフト制を含む交替制勤務であることで各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように早番、遅番で)異なることをもって「始業時刻等の変更」が措置されたことにはなりません。
参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)」
具体的なケースを想定して、制度設計を
改正育児・介護休業法への対応では、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が事業主の義務となります。制度設計のポイントとしては、実施可能な措置を念頭に置くことです。新たに制度を導入したとしても、その制度が労働者の職種や配置等から利用できないことが事前に想定できる内容であれば、事業主が措置義務を果たしたことにはなりません。企業単位で措置を考えるだけでなく、事業所単位、あるいは事業所内のライン単位や職種ごとに講ずる措置の組合せを変える等の工夫も視野に、現場で活きる制度の導入に目を向けましょう。