
労働関係法令上、労働者は「労務提供義務」を負い、一方で使用者はこれに対する「賃金支払義務」を負うという考え方の元、労働契約が締結されています。しかしながら、見方を変えてみると、労働者にとって労務の提供は一概に義務と言えません。労働者は働くことで賃金を得たり、スキルアップを図ったりすることができますから、これらの点でいえば「権利」とも捉えることができます。
「労働が義務か、それとも権利か」の解釈の相違は、ともすれば労使トラブルの火種ともなり得ます。今号では、労働者の就労請求権を争点とした判例を確認するとともに、労使トラブル回避のために雇用契約上、必要な企業対応を考えてみましょう。
目次
原則として認められない労働者の就労請求権
就労することが労働者にとって義務なのか、それとも権利なのかの議論について、過去の判例では、原則として「義務」であるという立場がとられています。冒頭でも触れたとおり、労働関係法令上、労働契約において労働者は使用者の指揮命令に従って一定の労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して一定の賃金を支払う義務を負担するとされているからです。労務提供の具体的な内容が使用者の指揮命令によって初めて特定されることを踏まえれば、使用者に対し想定しない労務の受領を強制することは困難と言えましょう。こうした背景から、労働者による就労請求権(締結された労働契約を前提として、労働者が使用者に対して自らの就労を求める権利)は認められないという考え方が主流となっています。
ただし、例外的に労働者の就労請求権が認められる場合あり
しかしながら、裁判所は以下の場合に、労働者による就労請求権を認めています。
① 労働契約等に就労請求権についての特別の定めがある場合
② 労務の提供について労働者が特別の合理的な利益を有する場合
①については、雇用契約書や就業規則の記載によります。就労の内容が明確に予定されたものであるか、就労が雇用契約上の権利とする旨の黙示の合意があるかどうか等により判断されます。
②については、従事する仕事内容から、就労が単に労務を提供するというだけでなく、労働者の職業能力を維持する上で不可欠な行為であるかが問題となります。過去の判例では、働く機会が与えられないことによって技量が著しく低下するとして、調理人による就労請求権が認められた事例があります。
就労請求権に関わる判断は一概に言えるものではなく、個別の事由による
最近の判例では、大学で教授の地位にあった労働者が、平成28年の秋以降、同大学が講義を一切担当させなかったのを不服とした裁判で、東京地方裁判所が労働者の就労請求権を認め、債務不履行による慰謝料等の支払いを命じたものがありました。このケースでは、雇用契約書に「最低でも週4コマ」という時間数の明記があったことから、同大学には講義を担当させる義務があったと判断されたとのことです。
ただし、過去の判例をみると、裁判所の立場ではあくまで「労働者は使用者に対する就労請求権を有さない」とするのが一般的のようです。
雇用契約上の労使トラブルを生じさせないためには?
実際の裁判で労働者による就労請求権を認めさせるのは難しいとはいえ、企業側が労働者との雇用契約を軽視して良いというわけではありません。企業は適正な雇用契約締結を徹底し、そもそも労使トラブルを生じさせないよう努めることが肝心です。
そもそも労働者から就労請求権が主張されるような事態にならぬよう、企業側が留意すべきことを考えてみましょう。
労働契約の大前提は、「労使間で信頼関係が構築されていること」。労使双方が信頼を損ねる言動を慎み、誠実に労働契約の締結・履行に努める姿勢を貫くことが大切なのではないでしょうか?企業側に求められるのは「契約通り仕事を任せること」、そして「法令遵守」です。










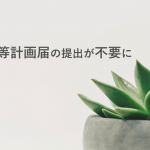

.pptx-10-150x150.jpg)












