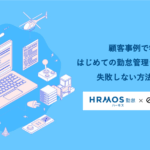政府主導の「働き方改革」に関わる議論が、いよいよ大詰めとなってまいりました。
昨年度末には「働き方改革実行計画(案)」が公表され、注目されていた「時間外労働の上限規制」の方向性が示されましたね。この件については、既に『労働基準法改正まであと2年!「残業時間100時間」が上限規制に?』にて解説した通りです。
4月以降はさらに労働条件分科会による審議が重ねられ、6月5日、「時間外労働の上限規制等について(報告)」が厚生労働大臣に建議されました。本報告書においては、“時間外労働の上限規制の枠組み”が改めて明らかにされると同時に、目新しいところでは“管理監督者を含む全労働者の労働時間の客観的把握”の必要性に関わる言及があり、注目を集めています。
「時間外労働(残業)の上限」は、単月で「100時間未満」、複数月では「平均80時間以内」
まずは、時間外労働の上限規制の基本的枠組みが、最終的にどのような形で決着したのかを確認しましょう。
結論から言えば、以前の記事でご紹介した「働き方改革実行計画(案)」から大きな変更はありません。ここでは、主な内容を抜粋してご紹介しておきます。
- 時間外労働の上限規制は、原則として「月45時間、かつ、年360時間」とする
一年単位の変形労働時間制(3ヵ月を超える期間を対象期間として定める場合に限る。以下同じ。)にあっては、上限は原則として月42時間、かつ、年320時間とする
- 下記に挙げる特例を除き、上記を違反した場合には罰則を課すことが適当である
- 特別条項付36協定を締結している場合、上限は「年間720時間」とする
ただし、年 720 時間以内において、最低限、上回ることのできない上限として
下記①~③を設定する
① 休日労働を含み、2ヵ月ないし6ヵ月平均で 80 時間以内
② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満
③ 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外
労働を上回る回数は、年6回まで
既知の内容となりますが、今後は上記を前提とした働き方を改めて検討することになります。
今後は管理監督者の勤怠管理も必須となる見込み
今回の建議における重要事項の一つとして、「長時間労働に対する健康確保措置」をおさえておきましょう。昨今、長時間労働に起因する過労死が問題となっていますが、これを受け、報告書では「労働者の健康管理の強化」の具体的な手立てについて言及されています。
- 医師による面接指導
長時間労働に対する健康確保措置として、労働安全衛生法第 66 条の面接指導について、
下記の通り改正することが適当
(現行)時間外・休日労働が1ヵ月あたり 100 時間超の者からの申出により実施
↓ ↓ ↓
(今後)時間外・休日労働が1ヵ月あたり 【80 時間】超の者からの申出により実施
- 労働時間の客観的な把握
【管理監督者を含む】、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定することが適当
ここで注目すべきは、労働時間の把握について「管理監督者」も含まれる点です。現状、管理監督者の労働時間管理についてはノータッチとなっている会社も多いのではないでしょうか?今後ますます重要視される勤怠管理について、今一度見直してみる必要がありそうです。
「管理職=管理監督者」は適切であるか?
余談ですが、御社では誰が「管理監督者」に該当するか、正しく把握できているでしょうか?一般的には管理職とされる「課長」もしくは「部長」以上を指す場合が多いようですが、そもそもこうした役職の方は皆「管理監督者」として適切であるかどうかを考えなければなりません。数年前には「名ばかり店長」の問題が話題になりましたね。実態として管理監督者の権限を持たないことから労働者性が認められ、未払い残業の支払い命令が出た事例もありました。
労働基準法上、「管理監督者」とは、“労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者”とされており、必ずしも「管理職=管理監督者」となるわけではありません。この点、労使トラブルの火種となりやすいポイントですので、注意が必要です。
参照:厚生労働省「労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために」
無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUは、出退勤データから残業時間レポートや36協定時間超過レポート、有給管理レポートなどの分析レポートを出力することができ、企業における労務管理の適正化に活用可能です。
管理監督者もしっかり勤怠管理する仕組みを整えましょう。