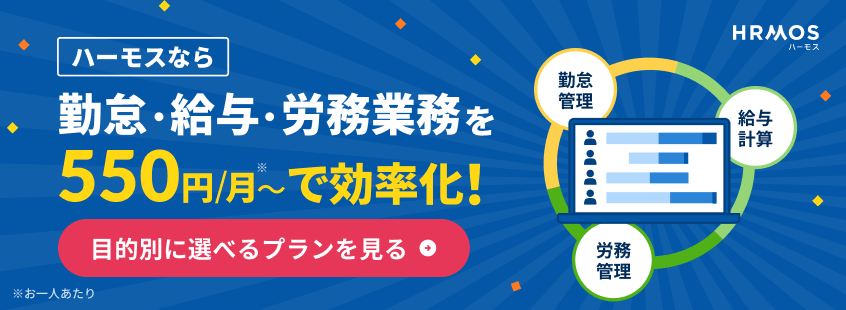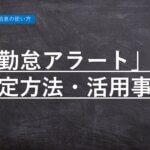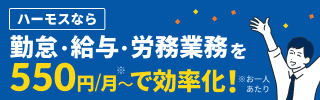2024年度雇用均等基本調査によると、2024年度の男性の育児休業取得率が40.5%と、過去最高を記録したことが分かりました。ここ数年で、子育て世代をとりまく就労環境は着実に変化し、「男性が育休なんて」というひと昔前の考えが大きく見直され始めています。今号では、男性の育児休業取得率向上の背景と、今後の課題について確認することにしましょう。
目次
2024年度の男性育休取得率が、前年+10.4%の「40.5%」に
 出典:厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」
出典:厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」
厚生労働省が公開する「令和6年度雇用均等基本調査」によると、2022年10月1日から2023年9月30日までの一年間に配偶者が出産した男性のうち、2024年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は「40.5%」となったことが分かっています。男性の育児休業取得率は、2023年度調査時の「30.1%」から 10.4ポイントも上昇しました。
男性育休取得率向上のきっかけは「育児・介護休業法の2022年改正」
これまで遅々として進まなかった男性の育児休業取得が急激に進んだのは、上図にも示される通り、2022年度以降です。2022年度といえば改正育児・介護休業法が施行された年であり、具体的には、4月から「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」、10月から「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」がありました。
関連:
打刻ファースト「男性の育休取得が義務化!?~改正育児・介護休業法~」
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」
育児・介護休業法の改正に対応できていますか?
社労士が専門とする法律の中でも、育児・介護休業法は、近年頻繁に改正が行われており、特に目まぐるしく変化する法律のひとつと言えます。男性の育休取得率向上の寄与した2022年改正の他、2025年度にも4月と10月に改正法が施行されています。打刻ファーストでもたびたび解説をさせていただいていますが、貴社では対応できているでしょうか?現状、未対応の項目がある場合には、早急に着手する必要があります。
関連記事:
『2024年5月31日公布の改正育児・介護休業法|7つの改正点と施行時期を総まとめ』
『改正育児介護休業法対応!2025年10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置義務」には事前準備が必須』
『2025年4月・10月施行!改正育児・介護休業法|他社の対応状況は?』
改正育児・介護休業法への対応をしていない企業は、民間の職業紹介事業者やハローワーク等により「求人不受理」の扱いを受ける可能性があります。そうなれば、貴社の人材確保に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。
関連記事:『2025年施行の改正育児介護休業法未対応で、「求人不受理」の可能性』
男性の育休取得に関わる今後の課題は「取得期間」の適正化
男性の育休取得率が「40.5%」に達し、政府が掲げる「2025年までに50%」の目標まではあと一歩となりました。このような男性育休取得率の向上の一方、要改善とされているのは「取得期間の短さ」です。
.png)
出典:マイナビ転職「育児離職と育休の男女差実態調査(2025)」
男性の場合、「2週間未満」が25.7%と全体の2割超を占めていることが分かります。もちろん、短期間であってもこれが従業員の意向に沿うものであれば、何ら問題はありません。しかしながら、「長期間の育休は取得しづらい」「本当はある程度まとまった期間取得したい」等の当事者の声を耳にすることも少なくありません。男性の育休取得が徐々に進む中で、取得期間についても改善が進んでいくことが望まれます。現場においては、男性従業員もある程度まとまった期間育児休業を取得することを前提に、職務設計や業務計画等の検討、職場環境の整備等に取り組むことが望まれます。