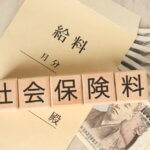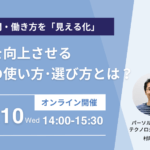「簡易型DC(簡易型企業年金)」って聞いたことがありますか?この制度は企業型確定拠出年金の中小企業向けで2018年5月にできた制度です。大企業では、俗に401Kと呼ばれている企業型確定拠出年金を企業の福利厚生の一環として以前から導入していますが、中小企業にとっては、この制度の導入は、手続きが煩雑で無理な制度でした。そこで、簡易な企業型確定拠出年金の制度を作ったのです。今回は、まだまだ知名度が低い簡易型DCについて解説します。
簡易型DCとは
DCとは、確定拠出年金のことで、個人型と企業型に分かれます。確定しているのは、拠出額(掛金額)で給付は運用状況によって従業員ごとに異なります。今までは、退職金として「確定給付企業年金」の制度を利用していた企業も多かったのですが、5~6年前から確定拠出年金に移行する企業が増えています。確定給付年金は、給付が確定しているため、低金利の状況では、運用がうまくいかず、その分会社も持ち出しが多くなるため、当然の帰結かもしれません。
確定拠出年金を企業に導入するためには、多くの手続きが必要となります。確定拠出年金規約を作成し、それとともに就業規則を変更し、厚生労働省に届出をして承認を得ます。この規約作成が大変で、これ以外にも多くの手続きが必要です。また、規約に変更が生じた時にも必要書類が多く、導入後の事務手続きも大変です。
簡易型DCは、この手続きをある程度パッケージ化することで、必要書類を削減して手続きを簡素化した中小企業向けのシンプルな制度です。
簡易型DCのメリット
通常の企業型DCは、手続きは面倒と言いましたが、その分自由度が高くなっています。例えば企業の掛金額の設定も複数あり、自社に合うように変更も可能です。その自由度を減らして、その分簡素化したのが簡易型DCです。
簡易型DCのメリットは、次の2点です。
①制度設計がシンプル
- 事業主掛金は定額で算定が簡単
- 加入者資格の設定は不要
- 少ない商品(2本以上)でも実施できる
- 制度設計がシンプルのため、事業主、従業員がわかりやすい
②手続きが簡単
- 制度設計に制限があるため、規約の申請時に必要な書類が13種類から5種類に大幅に減少
- 規約に変更が生じた時の必要書類や手続きが一部省力可能
- 業務報告書の簡素化
簡易型DCと通常の企業型DCの比較
簡易型DCは、従業員の合計が300人以下という制限はありますが、300人以下の企業であれば、簡易型DCと企業型DCのどちらでも選択することが可能です。
| 簡易型DC | 通常の企業型DC | |
|
制度の対象者 |
適用対象者を厚生年金被保険者全員に固定
※職種や年齢等によって加入是非の判断は不可 |
厚生年金被保険者
※職種や年齢等によって加入是非の判断は可能 |
| 企業の掛金額 | 定額 | 定額、定率、定額+定率のいずれか選択 |
| マッチング拠出 (加入者掛金額) |
選択肢は1つでも可 | 2つ以上の額から選択 |
| 商品提供数 | 2本以上35本以下 | 3本以上35本以下 |
| 従業員の規模 | 300人以下 | 人数制限なし |
出典:厚生労働省「2020年の制度改正」
簡易型DC導入の事業主のメリット・デメリット
①事業主のメリット
- 退職金制度を構築できる
退職金制度は、中小企業にとっては難しいことでした。あれば福利厚生の充実ということで、従業員の離職予防となるし、また新たな人材の確保にも有利となります。 - 会社のPRポイントとなる
掛金額が少なくても、「企業型年金やっています」というと企業イメージアップとなります。中小企業おいては、導入している企業は少ないので、優位にたてるでしょう。 - 節税となる
掛金は、全額経費となりますので、節税になります。
②デメリット
- 事務量が増える
手続き等簡素化されたといっても、やはり必要な書類の作成はあります。 - 掛金額を準備しなければならない
ただし、掛金額については初めは最低額でもいいかと思います。規約の変更の面倒はありますが、利益が出たら増やしていけばよいでしょう。 - 投資教育の必要性
実は、これが一番のデメリットかもしれません。DCにおいては、商品選択は従業員個人の自己責任です。だから資産が減ったのは本人のせいだと言われても納得できないかと思います。事実、DCの先進国であるアメリカでは、「DCの資産が減ったのは会社が投資教育を行っていなかったせいだ」と裁判で訴えられるケースが増えています。会社が導入した制度であるので、やはり会社が投資教育を行って従業員が商品の選択ができるようにすべきでしょう。毎年は必要ありませんが、最低でも新しく入社した従業員には、行うべきです。
まとめ_福利厚生を充実のために「簡易型DC」を一度検討してみては?
2018年に導入された「簡易型DC」ですが、その時は従業員100人以下の企業が対象でした。そのせいか、ほとんど導入する企業はありませんでした。ところが2020年には、従業員数が300人以下となり対象企業が増えました。しかし、まだまだ導入する企業は少ないのが現状です。制度の周知が今一つで制度自体を知らない企業も多く、厚生労働省の推進が望まれます。また、金融機関の営業が、掛金額や従業員数が多い大企業に偏りがちのため訊かないと教えてくれないという困ったケースもあります。しかし、中小企業にとっては、従業員の福利厚生を充実させる良い機会です。これを機に他社より少しでも早く「簡易型DC」を一度検討してみてはいかがでしょうか?