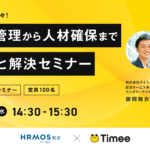人を雇ったら整えるべきは、「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」です。これらの「法定三帳簿」は、労務管理上、事業場に必ず備えておくべき書類であり、未整備の場合や法定の保存義務を果たしていない場合には「30万円以下の罰金」の罰則が適用になる可能性があります。
労務管理の法定三帳簿① 「労働者名簿」
労働基準法第107条は、事業場ごとに、雇用するすべての従業員1人につき1枚、労働者名簿の作成・保管を義務付けています。労働者名簿の記載事項は以下の8項目です。
- 労働者氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇用年月日
- 退職や死亡年月日とその理由・原因
「履歴」の欄には、原則として異動や昇進といった社内での履歴を記入しますが、労働者の社内外での履歴や学歴等を記録しておくことも問題ありません。
「従事する業務の種類」については、労働者が従事する業務や社内での役割を記入します。ただし、労働者数が30人未満の事業では記入しなくても良いとされています。
その他、社会保険の記号や番号、雇用保険番号等の情報を労働者名簿にまとめておくと実務上何かと便利ですが、「マイナンバー」の取扱いについては注意が必要です。マイナンバーは、現場においては特に慎重な取り扱いが求められる機密情報であり、「目的外保管禁止」とされています。よって、様々な労務管理書類に安易に記載することは厳禁であり、他の情報とは区別してマイナンバー単独で管理することとされています。
労務管理の法定三帳簿② 「出勤簿」
出勤簿は従業員の勤怠記録であり、具体的には以下の事項を記録し、保存します。
- 出勤日と労働日数
- 出社・退社時刻
- 日別の労働時間
- 欠勤した日の日付
- 遅刻・早退した日の日付・時間数
- 時間外労働・休日労働を行なった日の日付
- 時間外労働・休日労働を行なった時刻・時間数
- 深夜労働を行なった日の日付
- 深夜労働を行なった際の時刻・時間数
2019年4月より義務化された「労働時間の客観的な把握」により、使用者は従業員の労働時間を適切な方法により把握・記録・保存することとされました。具体的には、「使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること」「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」等の客観的な方法による把握が必要となります。
ただし、「使用者自らによる現認」は現実的に難しいと言わざるを得ません。また、「タイムカード」を用いた労働時間の記録は最も簡単な方法ですが、集計に手間がかかったり、保管場所の問題が生じたりします。この点、勤怠管理システムを活用して労働時間のクラウド管理に取り組むことで、集計の手間が省ける、収集データの分析が容易、膨大な量の資料を保管する必要がなくなる等のメリットが期待できるのでお勧めです。
労務管理の法定三帳簿③ 「賃金台帳」
賃金台帳は、勤怠データを元に、従業員の給与支給額、控除額を算出した資料です。記載すべき事項としては、以下に挙げる10項目があります。単に給与の支給額や控除額を記載するだけは足りないことから、給与明細で代用できるものではありません。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や時給、手当などの種類・額
- 控除の項目・額
「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」の保存期間は「5年」に延長されています
さて、冒頭では法定三帳簿の作成や保管を怠った場合には罰則の適用を受ける可能性がある旨に触れました。ここまでは「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」の必要記載事項について解説しましたが、最後に保存期間を確認しておきましょう。
従来は「3年保存」が原則だった法定三帳簿ですが、2020年4月施行の改正民法により、それぞれの保存期間は「5年」に延長されています(ただし、賃金台帳のみ、源泉徴収簿を兼ねる場合は法定申告期限から「7年」)。
労働基準法施行規則によると、各帳簿の保存期間の起算日は以下の通りです。書類の保存に際しては「いつから」「いつまで」を意識し、適切な取り扱いができるようにしましょう。
- 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 出勤簿については、労働者が最後に出勤した日
- 賃金台帳については、最後の記入をした日
参考記事:『タイムカード3年で捨てようとしていませんか?法改正で変わる出勤簿等の勤怠管理データの保存期間』
タイムカードによる勤怠管理、見直しませんか?クラウドを活用すれば、法令遵守の労働時間把握が可能になる他、勤怠データの管理・抽出・分析・保存が断然スムーズです^^無料で使えるクラウド勤怠管理システム「IEYASU」を、ぜひお試しください!