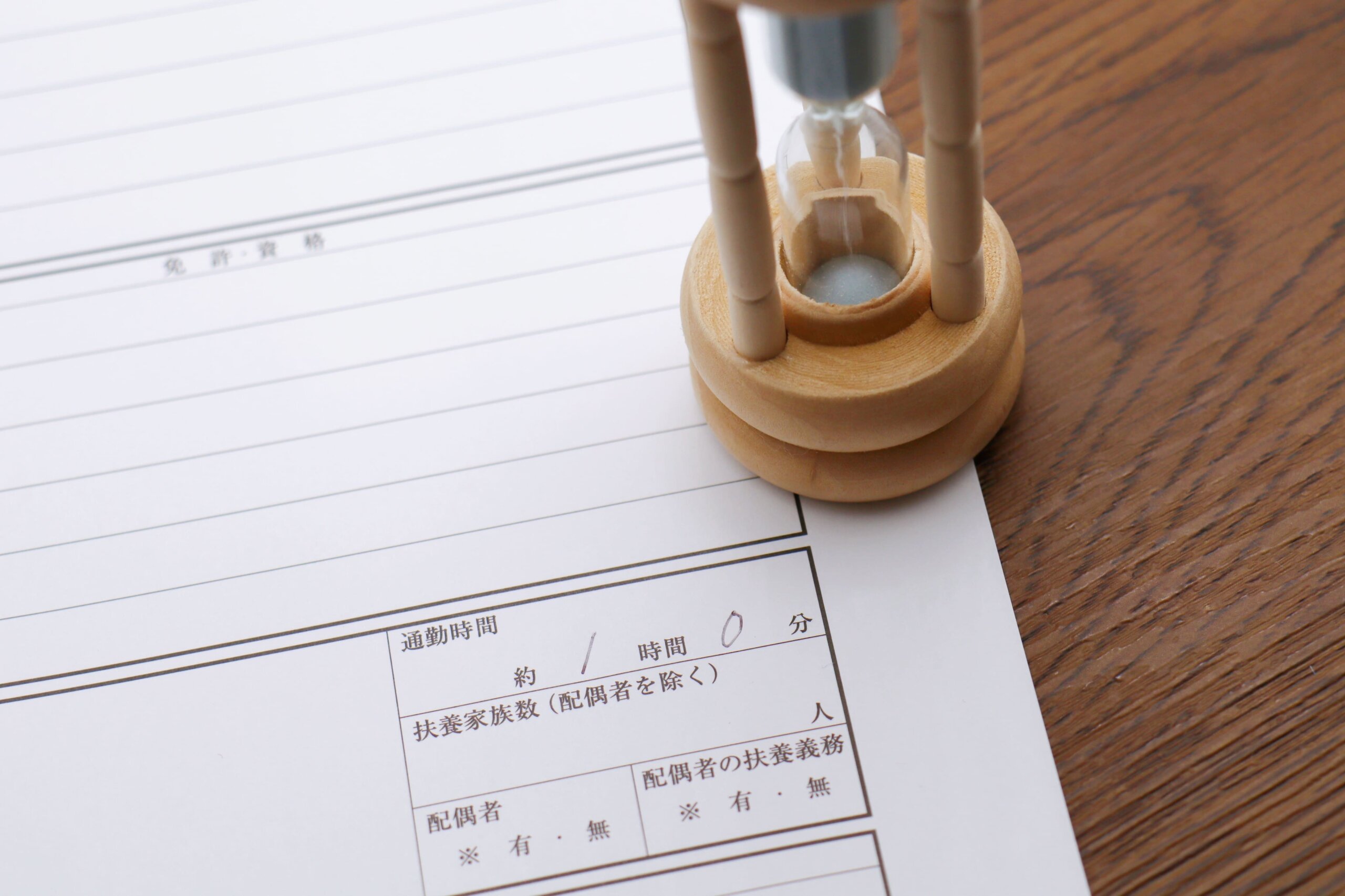
従業員の社会保険被保険者資格取得・喪失手続きは漏れなく行えている現場でも、被扶養者となった方のその後の資格確認に関しては、つい怠りがちになっているようです。こうした実態に鑑み、協会けんぽでは毎年10月に被扶養者資格の再確認を実施し、保険関係の適正化を促進しています。各事業場においては、毎年のことになりますが、被扶養者資格の確認作業にご対応ください。
目次
「被扶養者資格の再確認」とは?事業主が対応すべきこと
2024年度は10月上旬から11月上旬にかけて、協会けんぽから事業場宛に「被扶養者状況リスト」が送付されます。このリストを元に、被扶養者の現況確認を進めましょう。具体的には、事業業主が被保険者(労働者)に対し、現状、被扶養者となっている方が健康保険被扶養者要件を満たしているかどうかを確認する流れとなります。その後、被扶養者状況リストに確認結果を記入し、2024年11月29日までに返送します。
参考:協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認について」」
被扶養者認定の要件となる「収入要件」「同一世帯要件」
「被扶養者資格の再確認」に先立ち、事業主および被保険者(労働者)が、被扶養者として認定されるための要件を正しく理解しておく必要があります。
被扶養者の認定は、原則として以下の要件を満たしていることをもって行われます。
✓ 日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、
および次の(1)(2)いずれにも該当した場合
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・ 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・ 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者
配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
参考:厚生労働省「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
被扶養者の扶養解除に際し、「健康保険被扶養者(異動)届」のお手続きを
被扶養者が就職したり、収入が増えたりしたことにより被扶養者から外れる際は、「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。
参考:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
前項で解説した「収入要件」では「年間収入」の基準が挙げられていますが、この「年間収入」とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点及び認定された日以降の「年間の見込みの収入額」のことをいいます。被扶養者の年間収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。具体的に、給与所得等の収入がある場合で月額10万8,334円以上、雇用保険等の受給者の場合で日額3,612円以上の収入であれば被扶養者から外れます。
「被扶養者資格の再確認」は保険制度の健全化に不可欠
被扶養者資格の再確認の目的は、「保険給付の適正化」「保険料負担の軽減」を図ることにあります。例えば、本来であれば被扶養者とならない方が被扶養者として保険証を利用して保険給付を受けることで、不適正な保険給付が生じることになります。被扶養者資格を定期的に確認することで、各人が本来加入すべき保険制度から適正に給付を受けることができるようになるというわけです。
また、高齢者医療制度は、給付を受ける本人の負担の他、税金、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者から納められた保険料)によって支えられていますが、協会けんぽが負担する拠出金額の算出には被扶養者数も反映されます。つまり、被扶養者でない方の分、拠出金の過剰な支出が生じることになり、これにより保険料負担増につながる可能性が生じてしまうというわけです。
2023年度「被扶養者資格の再確認」では、およそ7.1万人の被扶養者が除かれ、被扶養者の解除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額は10億円ほどとのことです。各事業所においては、今一度「被扶養者資格再確認」の目的や意義を踏まえ、適切に対応できるようにしましょう!

























