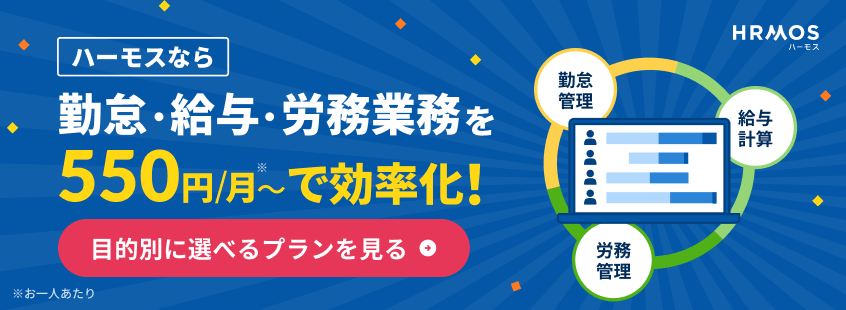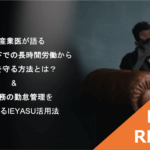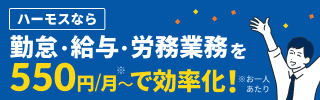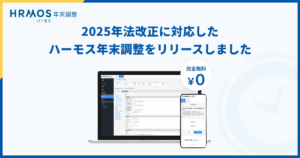従業員に対し、会社が一方的に自社商品・サービスの購入を強要するいわゆる「自爆営業」。かねてより民法及び労働関係法令上問題視されてきた商品の買い取り強要ですが、今後、労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)に基づく指針上に「パワハラ」として明記されることとなりました。主に販売ノルマを課せられることの多い業界においては常態化している自爆営業が、ようやく規制の方向で動きだします。
目次
「自爆営業」とは?パワハラとなり得る4つの類型
11月26日開催の労働政策審議会で、いわゆる自爆営業について、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当する旨をパワハラ防止指針に明記する方針が示されました。職場におけるパワーハラスメントの3要件とは、具体的には以下の通りです。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超える
- 労働者の就業環境が害される
パワハラ指針への明記に先立ち、厚生労働省はリーフレットを公開して、商品の買い取り強要等に関連して問題となる事例を4つ紹介しています。パワハラに該当する自爆営業の類型として、理解を深めましょう。
参考:厚生労働省「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」
ケース1 使用者としての立場を利用して、労働者に不要な商品を購入させた
自爆営業の典型となる「ノルマ未達成時の自社製品購入」については、以下2つの観点から問題があります。
〇 民法第90条(公序良俗)、第709条 (不法行為による損害賠償)
商品の買取り強要等に該当し当該労働者との売買契約が公序良俗に反して無効となり、また不法行為として使用者の労働者に対する損害賠償責任が認められる可能性があります。
〇 労働基準法第24条 (賃金の全額払い)
労働者に不要な商品を購入させた上で、賃金控除に関する労使協定を締結することなく購入代金を賃金から控除している場合には、賃金の一部を控除して支払うことを禁止した労働基準法違反となります。
※購入代金を労働者が直接支払う場合も、労働者が購入を断ることができない状況下においては、労働者保護の観点から不適切です
ケース2 自社商品の購入を断った労働者に対し、懲戒処分や解雇を行った
懲戒処分や解雇には、対象者の行為が企業秩序を著しく乱す行為であった等の合理的な理由が必要です。自社商品の購入強要は、それ自体、法的問題がありますから、これに応じないからといって処分を下すことができません。
〇 労働契約法第15条(懲戒権の濫用)、第16条(解雇権の濫用)
懲戒権又は解雇権の濫用として、当該措置が無効になるものと考えられます。
ケース3 会社が商品の購入を強要しなくても、購入せざるを得ない状況を作っている
従業員に対して売上ノルマを課している場合、就業規則等で、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益取扱いを受けることを明示しているケースもあります。このような場合、ノルマ達成のために労働者自身の判断で商品を購入する例が見受けられますが、やはり法的に問題視される点があります。
〇 民法第90条(公序良俗)、第709条(不法行為による損害賠償)
使用者が商品購入を強要していない場合であっても、労働者が高額の商品購入を繰り返している状況を知りながら放置しているような場合は、当該労働者との売買契約が公序良俗に反して無効となり、また不法行為として使用者の労働者に対する損害賠償責任が認められる可能性があります。
〇 労働契約法第15条(懲戒権の濫用)
ノルマ未達成を理由とした懲戒処分について、就業規則に規定がある場合であっても、単純にノルマ未達成だけを理由にこれらの措置をとった場合、当該措置は、懲戒権の濫用として無効となる可能性があります。
ケース4 高すぎるノルマを課す等、会社が積極的に自爆営業を促している
就業規則等で、ノルマ未達成の場合には人事上の不利益取扱いを受けることを明示しているケースでは、そもそものノルマが高すぎるために、自爆営業をせざるを得ない例も少なくありません。このような場合、達成が難しいノルマを課すこと自体、不適切と言えます。
〇 労働契約法第3条第5項(権利濫用の禁止の原則)、民法第709条(不法行為による損害賠償)
達成困難なノルマを設定することは、業務命令権の濫用として無効となる可能性があり、無効の場合は、ノルマを前提とした不利益処分も無効となります。さらに、このようなノルマの達成を指示することは不法行為として損害賠償責任が認められる可能性があります。
自爆営業の具体的な事例は、以下の資料からもご確認いただけます。
参考:内閣府「後を絶たない自爆営業」
自爆営業は「当たり前」「仕方ない」ではない!ハラスメントと認識して、適切な対応を
会社によっては、慣習的に自爆営業が行われていて、労使ともにその違法性に問題意識をもつことなくすっかり常態化しているケースも少なくありません。しかしながら、従業員の意に反した自社商品・サービスの購入強要には、法的にあらゆる問題があることに、改めて目を向ける必要があります。
自爆営業関連のパワハラ認定はこれまでにもありましたが、今後、自爆営業行為の法律上の位置付けや違法性の判断基準等が明確になることで、企業に対する制裁や労働者救済という観点が主流となってくるでしょう。現場においては自爆営業の違法性を改めて認識すると共に、経営陣の意識改革、自社の営業実態の把握に努める必要があります。